
11月も終わりに近づき、「年末大掃除」という言葉が頭をよぎり始める頃ではないでしょうか。
「でも、忙しくてまとまった時間が取れない…」
「どこから手を付けていいかわからない…」
と、焦りを感じている方も多いかもしれません。
大丈夫です!
大掃除は、年末に一気にやる必要はありません。
今回は、忙しいご家庭でも無理なく継続できる【1日15分】で進める大掃除・断捨離計画と、リバウンドしない「散らからない仕組み」の作り方をご紹介します。
この仕組みさえ作ってしまえば、心にゆとりを持って新年を迎えられますよ!
目次
無理なく続ける!【1日15分】断捨離・大掃除計画

大切なのは、完璧を目指さず「毎日少しずつ」継続することです。
タイマーを15分にセットして、指定の場所が終わらなくても「今日はここまで!」と潔く終えるのがポイントです。
【断捨離編】「パーツ別」で小さく区切る
断捨離は、物を捨てることではなく「持ち物を吟味する」作業です。
まずは小さなエリアから始め、達成感を積み重ねましょう。
🗓 1日目
財布・カバンの中:レシートや期限切れのポイントカードなどを処分。
🗓 2日目
キッチン引き出し一箇所:輪ゴム、クリップ、調味料など、雑多なものが集まる引き出しを整理。
🗓 3日目
子どものおもちゃ箱の隅:壊れたおもちゃ、パーツが足りないおもちゃを処分。
🗓 4日目
書類の山:期限切れの案内、必要のないDMなどを処分。
【大掃除編】「汚れ」に特化して集中する
汚れが落ちやすい今の時期に、重労働になりがちな箇所を少しずつ進めましょう。
🗓 5日目
ガスコンロ周り:油汚れを拭き取る。
🗓 6日目
洗面所の鏡とシンク:水垢を磨く。
🗓 7日目
窓のサッシ:ホコリや砂を掃除機で吸い取り、拭き上げる。
家族を巻き込む!「大掃除をイベント」にする魔法

大掃除をママ一人で背負い込むのは大変です。
家族みんなで協力すれば、効率が上がり、子どもにとっても「物を大切にする」教育の機会になります。
役割分担とルール作り
▶︎ 担当エリアを決める
パパ:普段手が回らない高所(換気扇、照明)や重労働(ベランダ、窓の外側)を担当。
子ども:自分の部屋や、リビングの「おもちゃを片付ける」など、責任を持てる範囲の作業を任せる。
💡褒めることを意識する
成果が完璧でなくても、「お手伝いしてくれて助かったよ!」「頑張ったね」と感謝の言葉で褒めましょう。家族のモチベーションを保つ秘訣です。
不用品は「賢く処分」する
断捨離で出た不用品は、すぐにゴミに出す以外にも、賢く循環させる方法があります。
◉ リユース(再利用):
状態の良い服や本は、フリマアプリで販売したり、地域の寄付団体に送ったりすることを検討しましょう。
◉ ウエスとして活用:
古くなったタオルやTシャツは、使いやすい大きさにカットして「ウエス(雑巾)」としてストックしておくと、大掃除の拭き掃除に役立ちます。
リバウンドを防ぐ!「散らからない仕組み」の作り方
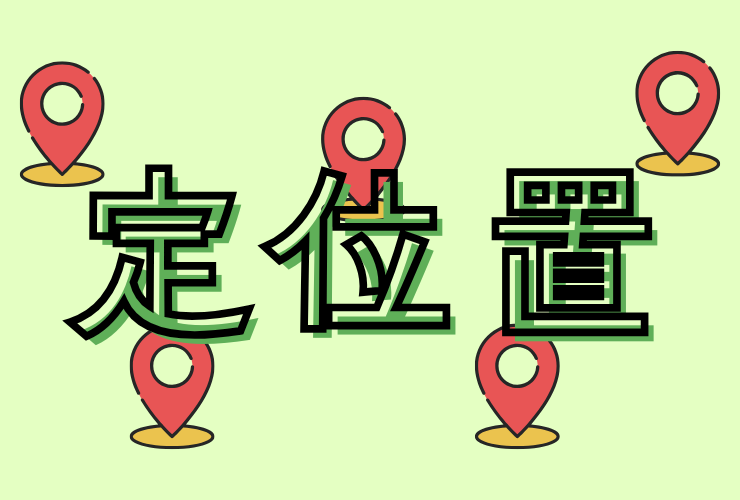
大掃除を終えても、すぐに部屋が散らかってしまっては意味がありません。物を減らしたら、次は「定位置」を作ることに集中しましょう。
🚩 「物の住所」を明確にする
💡 定位置を決める
すべての物に対して「ここにしまう」という住所を決めましょう。
使ったら「住所」に戻すことを家族共通のルールにします。
💡「とりあえずBOX」を置かない
「後で片付けよう」と入れる箱(とりあえずBOX)は、物の一時避難場所ではなく、散らかる原因になります。
しまう場所がなければ、それを機に処分を考えましょう。
👍 ワンアクション収納を目指す
◉ フタを開ける手間を省く
子どもが使うおもちゃや、パパがよく使うリモコンなどは、フタのないオープンボックス収納にしましょう。
しまう時の「ワンアクション」の手間を減らすことが、リバウンド防止につながります。
まとめ:心にゆとりを持って新年を迎えよう
「1日15分」の積み重ねは、年末に焦って一日中掃除するよりも、体も心もずっと楽です。
ぜひ、今から少しずつ取り組みを始め、「散らからない仕組み」を作りながら、家族みんなで心地よい新年を迎える準備を進めてくださいね。










